いよいよ2025年の大晦日、今年も皆さまには大変にお世話になりました。
現在68歳ですが、来年も月100kmの早歩きを目標にします。
今年目標にしていた、任天堂スィッチ「リング・フィット・アドベンチャー1回転」は、チャレンジする機会がめっきりと減ってしまい、1/3程度しか進みませんでした。
SNS投稿に関しては、「読んでみようかな!」と思ってくださる内容と思っているのですが、これがなかなか難しい。
どうでもいいような内容もたくさんあったと思いますが、お付き合いくださり本当にありがとうございます。
来年もお付き合いのほど、よろしくお願いいたします。
皆さま、良い年をお迎えください。





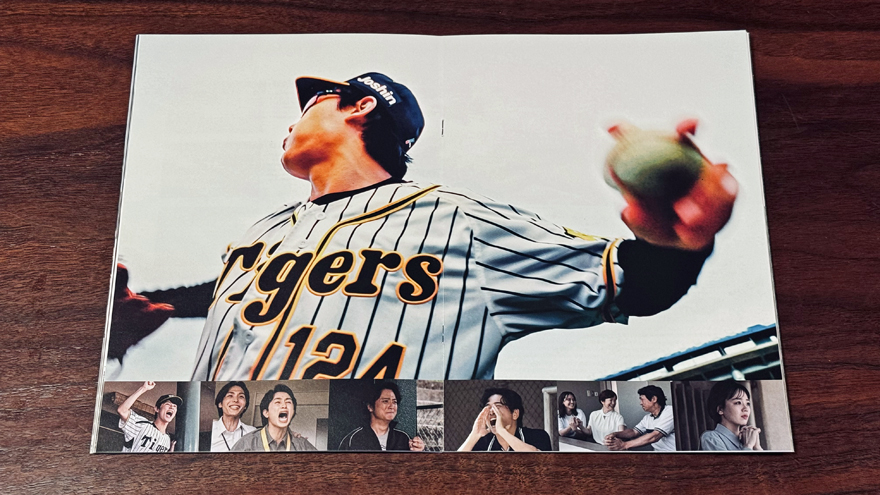

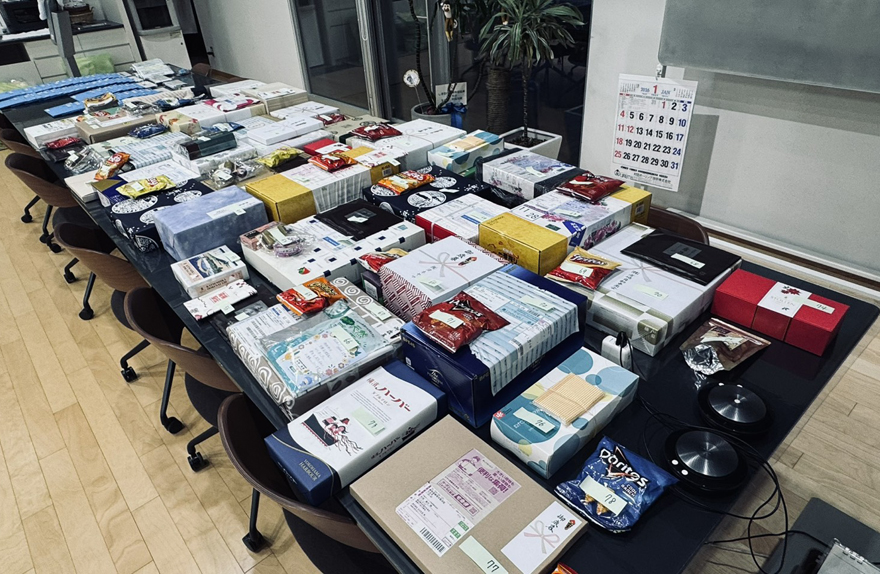
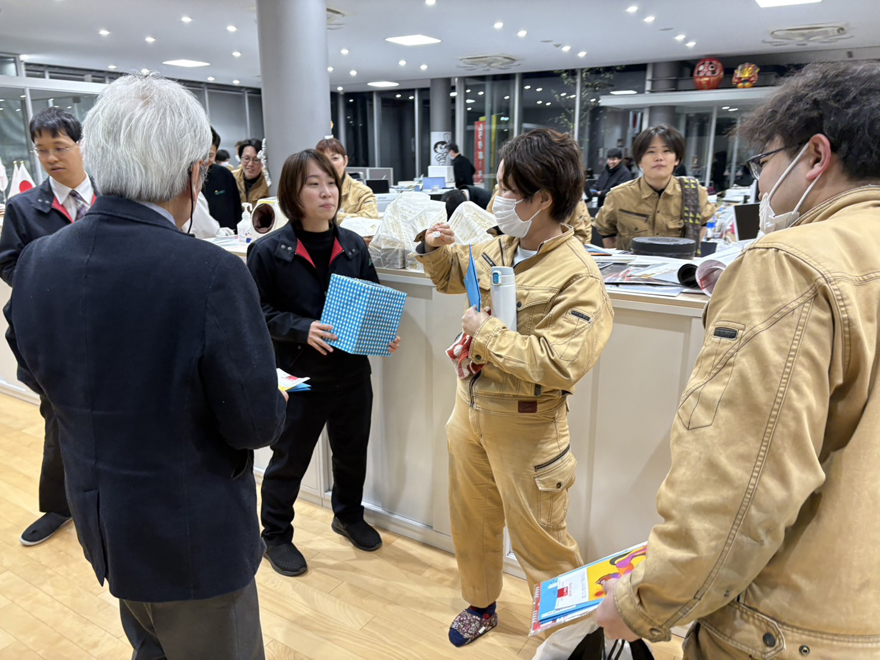










 可愛らしいぬいぐるみ
可愛らしいぬいぐるみ