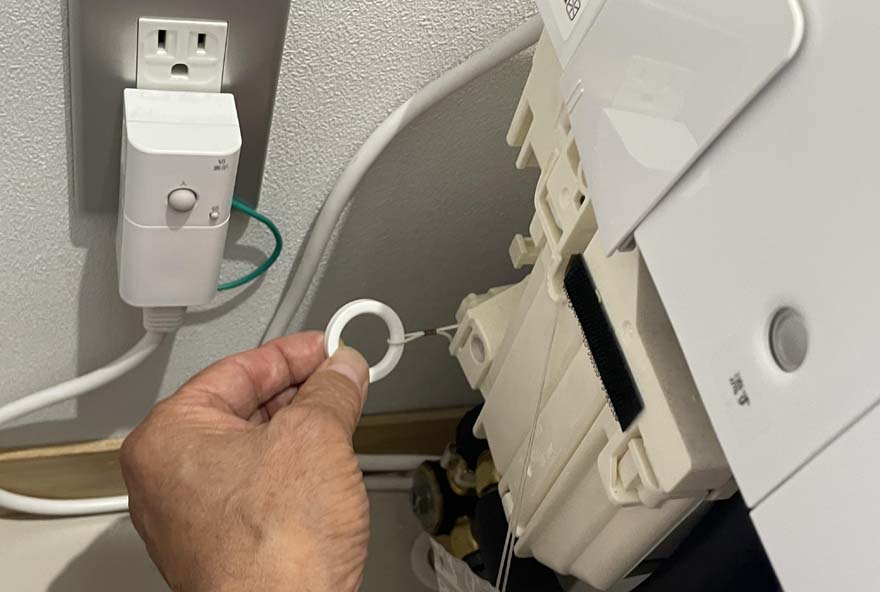一昨日、「生みそずい」についての記事を投稿しました。
するとSNSで、「“茶壺に追われて トッピンシャン”とは、どういう意味ですか?」というコメントをいただきました。
確かに、改めて考えると気になります。
そこで調べてみました。
■ 童謡「ずいずいずっころばし」
ずいずいずっころばし
ごまみそずい
茶壺に追われて
トッピンシャン
抜けたらドンドコショ
俵のねずみが
米食ってチュウ
チュウチュウチュウ
おっとさんが呼んでも
おっかさんが呼んでも
行きっこなしよ
井戸のまわりで
お茶碗かいたの
だあれ
■ 言葉の意味
「ごまみそずい」
「みそずい」とは味噌吸物、つまり味噌汁のこと。
ごま入りの味噌汁を指し、庶民の日常の食事を表している。
「茶壺に追われて」
江戸時代、宇治の新茶を将軍に献上するための行列「茶壺道中」は非常に格式が高く、庶民は行列を見かけると土下座して道を譲らなければなりませんでした。「追われて」という言葉には、自由に動けない庶民の立場や緊張感が込められています。
「トッピンシャン」「ドンドコショ」
意味のない囃子言葉で、歌にリズムや遊び心を加えるための表現です。
「俵のねずみが米食ってチュウ」
米は生活の糧であり財産。その米をねずみが食べる様子は、庶民の不安や現実的な悩みを象徴しています。
「行きっこなしよ」
「行くことができない」という意味。権力や決まりに逆らえない状況を表しています。
「だあれ」
子どもたちが輪になって遊ぶ際の問いかけで、遊び歌としての要素です。
■ この歌が伝えているもの
「ずいずいずっころばし」は、江戸時代の庶民の暮らしや権力に対する緊張感、日常の食事や不安を、歌や遊びに変えて楽しむ“したたかさ”を、子どもの遊び歌という形でやさしく包み込んだ歌だと考えられている。
背景を知ると、童謡ひとつにも、当時の暮らしや思いが込められていることが分かります。
なるほどねぇ・・・!






 新聞折込
新聞折込