今朝のNHK BSで「江戸のおやつ」という番組を放送していました。
「おやつの語源って何?」
ということで調べてみました。
江戸時代の時刻制度では、一日を「十二刻(子・丑・寅…)」で区切っており、今の時刻に当てはめると、午後2時ごろが「八つ時」と呼ばれていた。
当時の人々は一日二食(朝と夕方)が基本だったため、午後2時ごろに小腹を満たすために軽く食べる習慣があり、この風習が「お八つ」(おやつ)の語源となる。
やがて「八つ時に食べる軽い食事」が省略されて「おやつ」となり、現在では時間に関係なく子どもが食べるお菓子や軽食・間食全般を意味する言葉として使われるようになった。
「なるほどねぇ~!!!」
 |






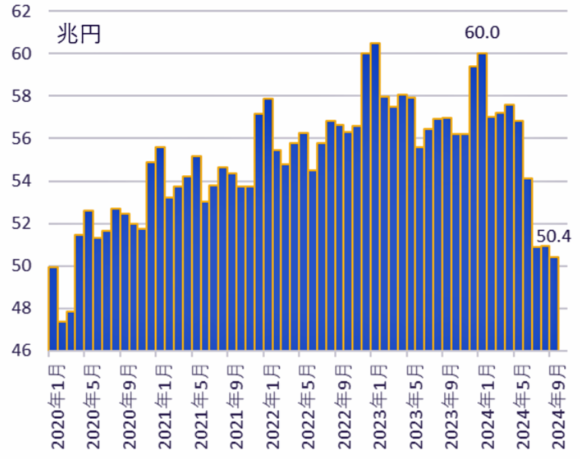


 革靴
革靴