私の不得意としている事かもしれません。
もともと話しが上手くないので、思っていることがそのまま伝わらないことがあります。
大久保寛司さんは「相手の立場から物事を見ながら、考える」ということが重要だと。
「自分が何を言ったか」ではなく、「相手にどう伝わったか」がはるかに大事であり、思いがが行動になってはじめて成果を生み出すことになるので、行動として実践されない限り「思いは伝わっていない」ということになる。
「なぜわからない」と相手に指を向けるのではなく、「どうすれば理解してもらえるか」と、自分に改善の指をむけるようにすることだと。
つい相手が悪いと言い勝ちですが、常に自分に指を向けることが大事ですね・・・・。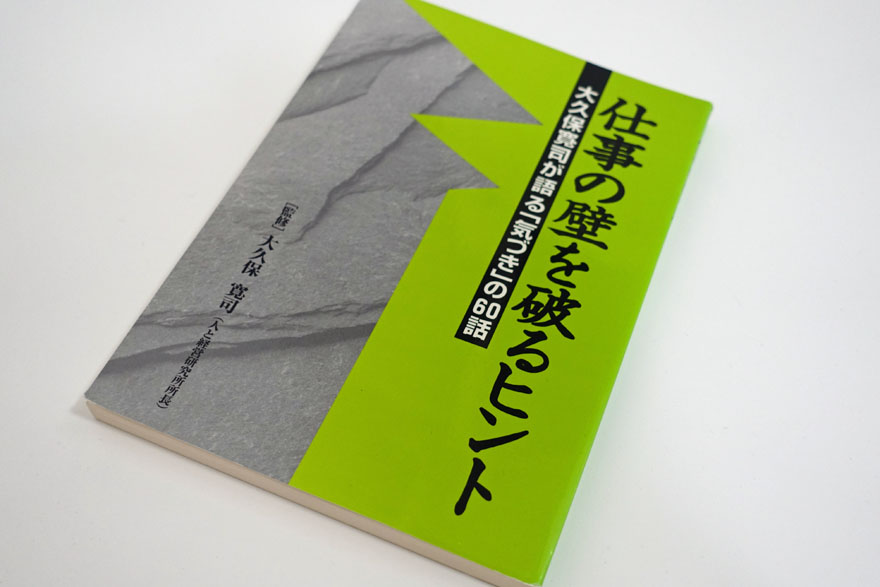
大久保寛司「仕事の壁を破るヒント」
2016_11/16
思いは相手に伝わっているか?
2016_11/07
補い合いが大事ですね!
恋愛中は「相手のためなら何でも尽くす!」と思っていたのに、結婚した途端にお互いが相手に要求することが増え、熱が覚めて行く。
最大の要因は「お互いに求めることが多くなるから」ではないでしょうか?
求めることが叶わないと不満になる。
人間、それぞれ得手不得手があるので、そこを求めても仕方ありません。
夫婦円満になる秘訣は、不得手なところはお互いに補い合いをすることじゃぁないかなぁと思います。
幻想的な空模様
2016_10/30
硬い殻を破ろうとする意識を持ちたいものです!
日々生きているうちに身に付いてしまう固定概念という殻!
歳を取れば取るほど硬く、そして厚くなる。
小さい箱に入れられて、それ以上飛べないという条件付けされたノミは、箱を取り去ったとしてもジャンプしなくなるといいます。
人間も「あれはできない」、「これはできない」と自ら条件付けをしてしまう生き物。
本当はできるのに・・・。
果たして自分はどうなのかと振り返えれば、かなり小さい箱じゃぁないかと。
殻を破る努力をすること、大事ですね!
曇り空
2016_10/29
お金は、入るより出る方が先!

村田光生(左)と五日市剛さん(右)
2016_10/28
魂の成長!
生まれ変わりって、あるように思います。
仏教でいうところの輪廻転生。
生きていると「この場から逃げだしたい」と思うような苦難の1つや2つはあるもの。
そういうような時に、「前世でやり残したことかな?」と思うようにしています。
この世でも逃げると、「まだまだ学びが足りないな」ということで来世でも同じようなことが繰り返される。
「そう、それを乗り越えるまで・・・・!」
嫌なことに立ち向かうことで、人の器が大きくなる。
それと同時に、魂も成長することで次はレベルアップしたステージに立つことができるんじゃぁないかなぁ!
幻想的な空模様
2016_10/24
人は理論では動かない!
バブル時代は、うんもスンもなく早朝から夜遅くまで精力的に働くのが当たり前の時代。
仕事が嫌とか、人間関係がギクシャクしていようがいまいが、目の前にある膨大な仕事をこなすことに全力集中でした。
しかし、時代は変わり、より仕事に集中させる環境を作ることが必要な時代になったように思います。
トヨタ自動車の豊田章男社長が「私の家庭教師」といわしめる伊那食品工業の塚越寛会長は、「やる気を持った人と、そうでない人の差は3倍違う」と語っています。
どうやら、いかにやる気を持って仕事に集中してもらう環境を作ることで、生産性が上がることは間違いなさそうです。
2016_10/17
人生にリハーサルはない!
「人生にリハーサルはない」
42年前に受講したセミナーで講師が言われた言葉ですが今でも強烈に記憶に残っています。
「座右の銘」とか「寄せ書き」などの時には、この言葉を好んで書きます。
できれば悔いのない人生を歩んでいきたいですね。
気持ちの良い空模様

