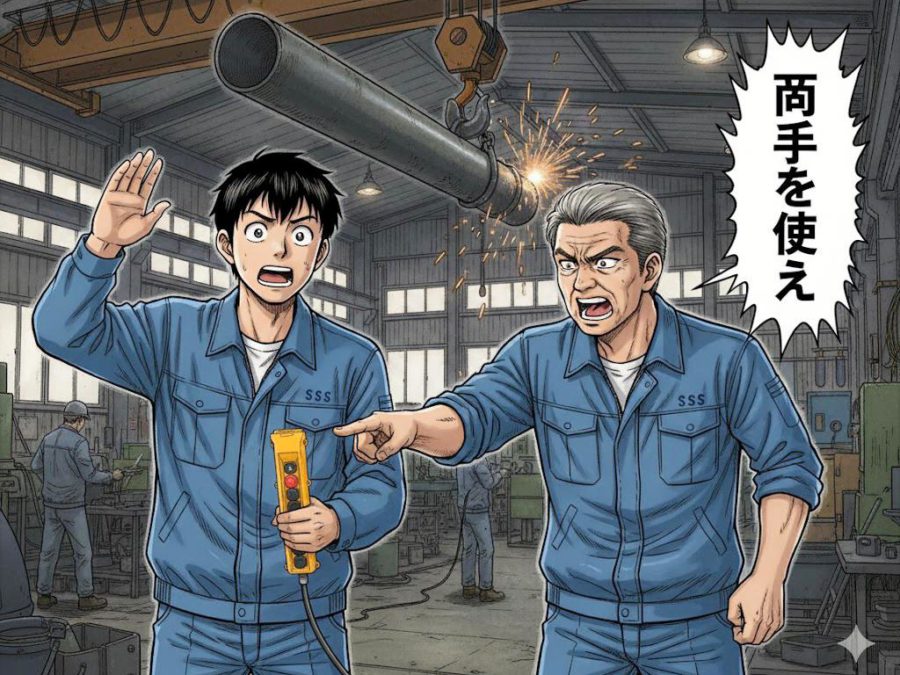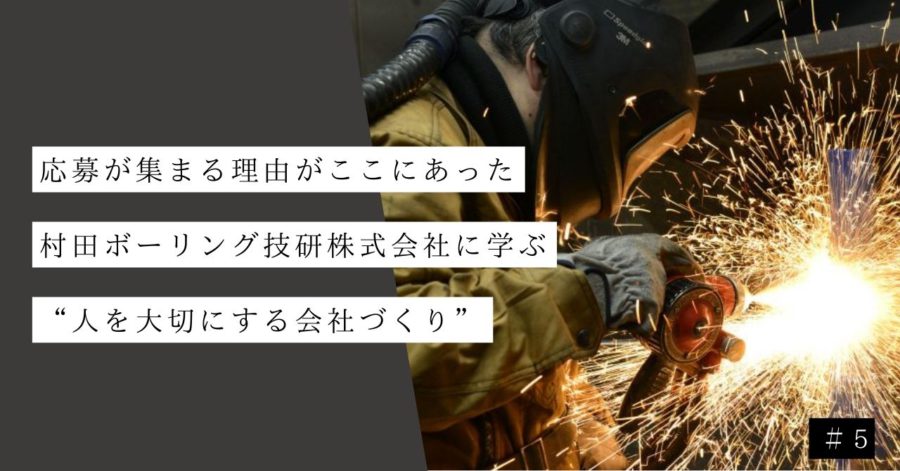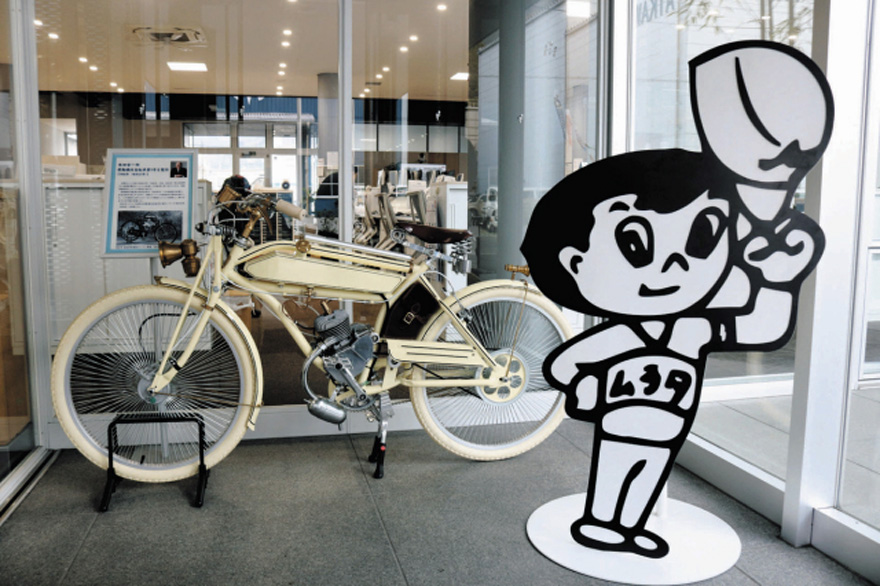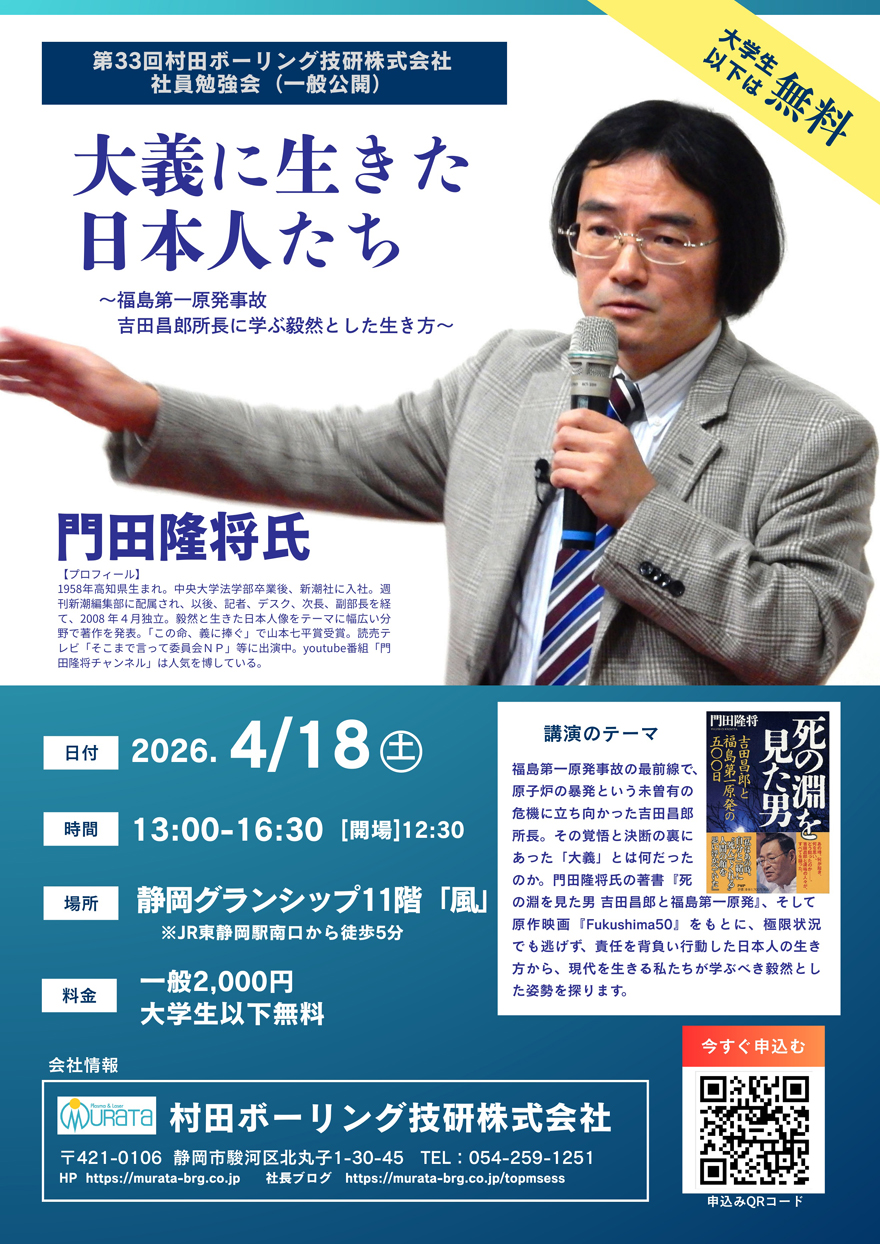2005年12月27日に「溶射屋ブログ」をスタートしてから、早いもので21年目に入りました。
2008年8月5日からは連続投稿中。
日々ブログを書くことは、私にとって何よりの「自分磨き」となっています。
それ以外にも、毎日発信し続けることでしか得られないメリットを、身をもって感じている一人です。
出会った方々に「ぜひ毎日投稿してみてください」と勧めすることもありますが、実際に投稿する方は、残念ながら一人もいらっしゃいません。
日々投稿している人だけしか感じられないメリットがあるの残念ながら伝えられません。
投稿したブログは、サーバーに記録が残る限り、末永くこの世に刻まれます。
それはつまり、私の「想い」が子孫へと受け継がれていくということでもあります。
少なくとも、今いる6人の孫たちが成長した時、この記事を読めば「おじいちゃんはこういう考え方で生きていたんだな」と分かってもらえるはず。
未来の孫たちへ贈る、心のバトン。
これからも、日々の気づきを大切に書き残していきたいと思います。
写真は3年前、次女夫婦の長男の一升餅のお祝いにて。この後さらに2人の孫が生まれ、今は6人となっています!