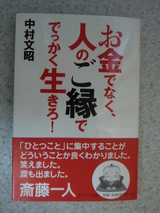昨日、岬龍一郎先生をお呼びしての「静岡岬塾」をぺガサートで開催しました。
昔、世界に誇れた「武士道」精神があった日本。
1921年アインシュタインが6週間日本に滞在した際のの最後の講演会で下記のことを言ったという。
「近代日本の発展ほど世界を驚かせたものはない。
一系の天皇を戴いていることが今日の日本をあらしめたのである。
私はこのような尊い国が世界に一ヶ所ぐらいなくてはならないと考えていた。
世界の未来は進むだけ進み、その間幾度か争いは繰り返されて、最後の戦いに疲れる時が来る。
その時人類は、まことの平和を求めて、世界的な盟主をあがなければならない。
この世界の盟主なるものは、武力や金力ではなく、あらゆる国の歴史を抜きこえた最も古くてまた尊い家柄でなくてはならぬ。
世界の文化はアジアに始まって、アジアに帰る。
それにはアジアの高峰、日本に立ち戻らねばならない。
われわれは神に感謝する。
われわれに日本という尊い国をつくっておいてくれたことを 」
それに比べて世界からエコノミックアニマルとまで嘲笑されるようになってしまった日本。
岬先生はそんな日本の若者に「武士道精神を説くことによって」少しでも変化させようと全国を重病を患った身体で回っています。
今回は私も所属している「駿河財団 http://www.zai.jp/page020.html」のメンバーの一部の方にも参加してもらうことができ本当に良かった。
懇親会も盛り上がりましたね(笑)
岬先生は2ヵ月ごと静岡で勉強会を開催しておりますので次回は11月、今回参加できなかった方次回は是非お越し下さい。